ナミビア南部貧困地域における非就業者の扱われ方についての人類学的研究
対象とする問題の概要 ナミビア南部に主にナマ語を話す人々が生活する地域 がある [1] 。この地域は非就業率と貧困率が高く、多くの非就業者は収入のある者や年金受給者と共に生活し、その支援を受けている。1990年代初めに地域内の一村で調査を…

湾岸地域の小国カタルは、域内の大国サウディアラビアとイランに挟まれている。これは地理的な関係のみならず、政治的にも両者との関係が発生することを意味している。サウディアラビアとイランは域内のライバルであることから、一方に与すれば一方に仇なすことを意味する。そのためカタル王政にとって両国との関係は安全保障政策における最も重要な問題であり続けてきた。独立後は親サウディアラビアの方針であったが、1995年に現首長の父ハマドが権力を掌握すると、徐々にサウディアラビアとの距離が開いていった。更に2011年政変により湾岸諸国の国際的なプレゼンスが高まると、湾岸域内の関係が変容した。その最たる事例が、本研究の主眼たる2017年6月のカタル危機である。この危機によりカタルはサウディアラビアなどの周辺諸国から断交され、独立以来最大の安全保障上の危機となっている。現在もこの危機は続いており、今後の湾岸情勢を左右すると考えられる。
本研究の目的は 2つに分けられる。まず2011年政変から現在に至るまでの湾岸地域の政治経済史をまとめ、域内関係がどのように変容したかを整理する。これによって、湾岸域内関係がサウディアラビア対イランという二項対立ではなく、より複雑な複層的構造である事が明らかになると考えられる。具体的には、カタルとサウディアラビアの域内での外交政策の衝突や、それによって生じた地域統合の停滞などがあるのではないかと考えている。更には、サウディアラビアのムハンマド皇太子、カタルのタミーム首長、アラブ首長国連邦のムハンマド皇太子という若手による、湾岸の次世代の覇権を巡る争いも存在する。
次に、本研究は本邦のエネルギー安全保障に学術分野から貢献する事を目的としている。石油資源の 99% を輸入に依存する本邦は、その内の 85% を中東から輸入している。この事からも、中東の目まぐるしい情勢を把捉する事は重要であると考えられる。
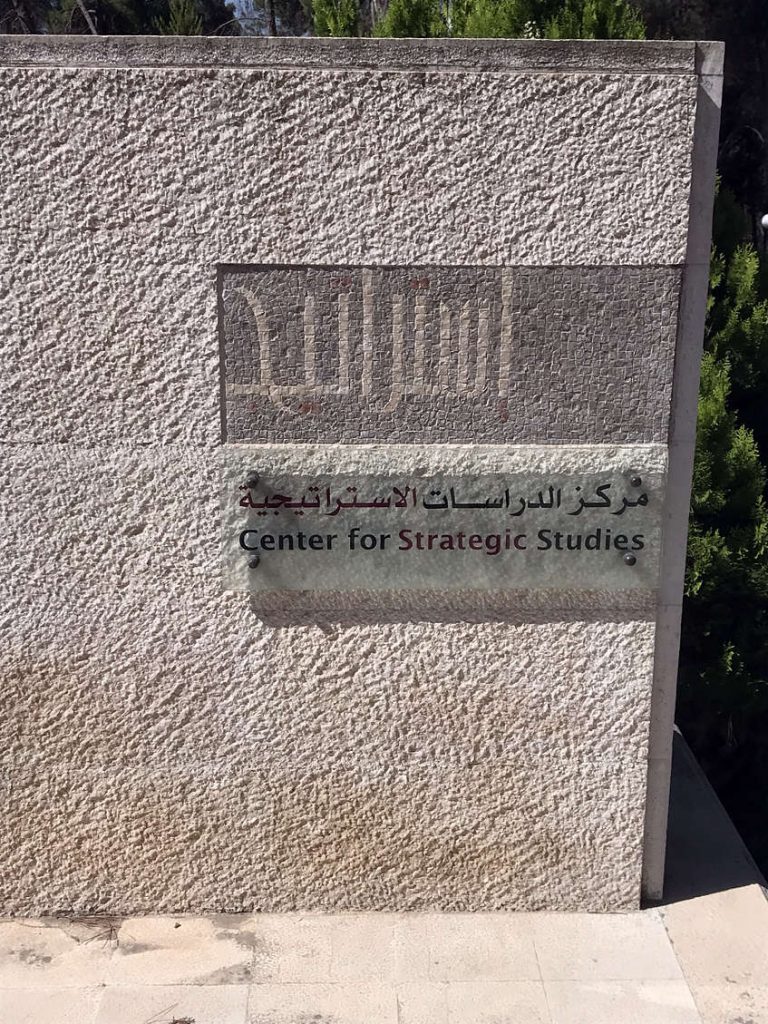
渡航調査先のヨルダン・ハシェミット王国は、シリアやレバノンなど近隣の不安定な諸国と対照的に、政治的安定を享受してきた。その外交方針は、「中東地域の穏健勢力としてアラブ・イスラム諸国との協調、全方位等距離外交の推進を基調。」と評されている 。筆者が渡航した際にも、様々な政情により移民・難民としてヨルダンに辿り着いたという経歴を持つ人々が大勢いた。出身地としてはパレスチナ、シリア、イラク、イエメン、エジプト、スーダンなどが挙げられる。彼らの大半が「政治・経済的事情で祖国を去らねばならなかったが、ヨルダンには感謝している。」と語っている事からも、ヨルダンの全方位等距離外交が広く支持されている事が伺える。
ヨルダンを範とした湾岸版バランサーを志向したのがカタルではないかと、筆者は渡航中に幾度も感じた。これは近年のGCC 諸国のプレゼンスの高まりにより、カタル危機の発生や、域内外の危機に対応する為に結成された GCC という組織の存在理由を失わせた事にも関係すると考えられる。2003年までの湾岸地域はイラン・イラク・GCC 諸国の対立であり、勢力均衡が模索されてきた。しかしサッダーム・フサイン政権の崩壊やイランの核開発疑惑を巡る制裁などにより、2000年代後半から湾岸地域内の勢力均衡は崩れ始めた。更に 2011 年政変により湾岸域外の諸国 (特にエジプト) が崩壊すると、GCC 諸国のプレゼンスは向上した。その結果 GCC 諸国内の対立が顕在化し、現在のカタル危機の一因となっているのではなかろうか。カタルはヨルダンと同様国土が小さく、軍事的にはサウディアラビアやイランからの脅威を取り除く事は出来ない。その為カタルはアメリカやトルコといった大国との関係を維持し、安全を保障する方策を採用してきた。これはヨルダンがアラブで数少ないイスラエルと国交を有し、全方位等距離外交を模索してきた事と類似している。ヨルダンで出会った人々から、思いもしない研究上の閃きを得る事となった。
第一に、ヨルダンという湾岸域外の国に渡航して、湾岸地域をより広い視野で再考する機会を得る事が出来た事は大きな成果であると考えている。この着想を無駄にする事なく、カタルの安全保障に関して研究を進めていきたい。こうした個々の国家の視点に加え、よりマクロに湾岸域内関係の変容についても GCC やイランと GCC 諸国の関係性などを中心に論じていきたい。
第二に、研究対象であるカタル渡航への大きな弾みとなった。中東の気候や文化、政情などは本邦と異なり、それらに対処するには一程度の「慣れ」が必要とされる。筆者が中東を訪問するのは 2016年以来であり、渡航初日は強い日差しや脱水により体調を崩しかけた。更に口語アラビア語に対応するのにも日数を要する。それらをカタルに渡航する前に経験する事が出来たのは、非常に貴重な機会であったと感じている。この「慣れ」が冷めぬ内にカタルに渡航し、より実り多い調査を行いたいと考えている。
Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.