木材生産を目的とする農林複合の可能性 /タンザニア東北部アマニ地域を事例に
対象とする問題の概要 アフリカ諸国では、高い経済成長を遂げたことで、人口が急激に増加している。家屋を建てた後に人々が求めるものは、ベッドやソファなどの家具であり、その材料には耐久性の優れた天然の広葉樹が用いられてきた。しかし、天然林への伐…

西アフリカは、サブサハラアフリカの中でも布を仕立てた服の着用が多く見受けられる地域である。人々は市場で布を買い、布を仕立屋に持っていき、自分好みのスタイルに仕立てる。布で仕立てた服は日常着から結婚式などの特別着としてまで幅広く使用され、人々の生活の隅々まで行き渡っている。その一方で、現代アフリカにおいてはライフスタイルの変化や諸外国からの大量の古着の流入が見受けられる。このような変化の中で、西アフリカの人々はどのような動機で布から仕立てた服を着用しているのだろうか。そして、その背景にはどのような価値観があるのだろうか。本研究は西アフリカにおける布を仕立てた服に着目し、その着用をめぐる人々の実践やその背後にある価値観を探っていく。
現在、サブサハラアフリカ地域には、先進国をはじめとする諸外国から古着や廉価な衣服が大量に流入している[福西 2014]。また、服の仕立てに使用されるプリント布の誕生には、ヨーロッパの世界進出や産業革命、植民地支配が深く関わっている[グロフィレー 2019]。このような歴史的背景をもつプリント布は、現代において必ずしも西アフリカ地域で生産されているとは限らない。ヨーロッパをはじめとするアフリカ域外で生産されていることも多く、現在は中国産の布も増加している。実際に、サブサハラアフリカの他の地域をみると、Tシャツやジーンズなどの既製服の着用が浸透している地域も多い。それでは、西アフリカの人々は一体プリント布をどのような動機で着用し、洋服と使い分けているのだろうか。そして、必ずしも「アフリカの布」とは言えないプリント布をどのように受容しているのだろうか。
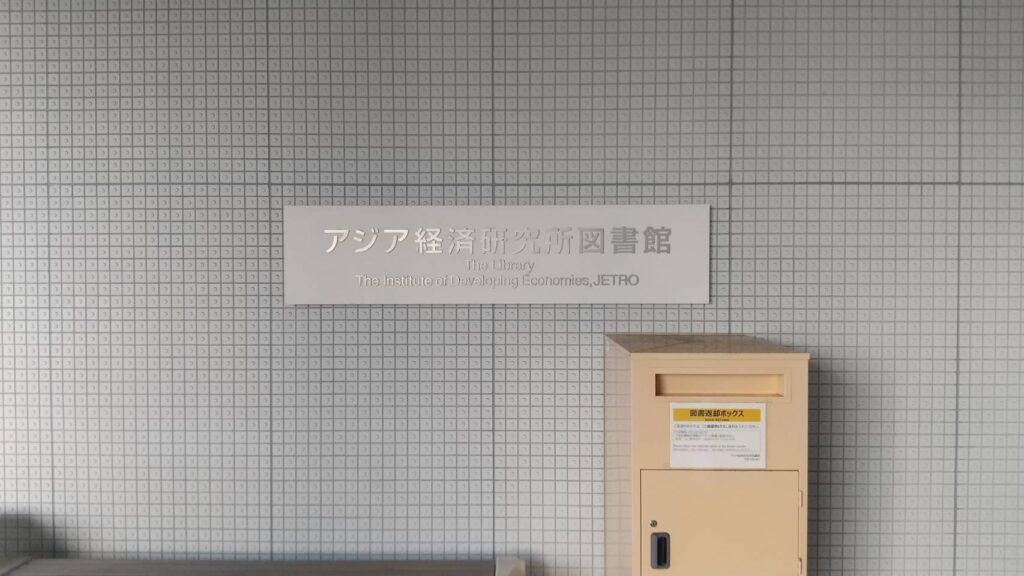
本調査では、西アフリカ出身の女性5人(セネガル、ナイジェリア、ガーナ、マリ)への聞き取り調査を行った。その結果、布にもランクがあること、また布の生産国によってその布に対する評価が異なるということ、またプリント布やファッションに関する情報の入手方法については、InstagramやFacebookなどのSNSが多いということが分かった。また、近年布を仕立てた服の着用状況に変化が生じているということも明らかになった。国内産の布で仕立てた服を着用することを政府主導で奨励する動きのある国(ガーナ)や、国内統一のために積極的に他の民族の布を取り入れる動きのある国(ナイジェリア)があるということが分かった。また、今回の聞き取り調査の中では、「民族服」や「伝統」という言葉がよく出てきた。プリント布で仕立てた服を身に付ける動機には、デザインの好み、アイデンティティ、宗教規範、民族意識などが関わっていると推測できる。今回の調査では、布の種類が国や地域、民族によって異なること、そして同一の布であっても国や地域、民族によっても呼称が異なるということが明らかになった。また、布を仕立てた服の着用は、宗教とも深く関わっており、モスクや教会に行く際には、布で仕立てた衣服を着用している。これらのことから、布を仕立てた衣服は民族や宗教と深い関係があるということが示唆される。
今後実施予定の調査では、今回聞き取り調査を行った5人の西アフリカ出身女性へのさらなる聞き取り調査を行いたいと考えている。それに加え、日本在住の西アフリカ出身の仕立屋の方への聞き取り調査を行うことも想定している。さらに今後は、現在日本に住んでいる西アフリカ出身の人々にとって、布から仕立てた服が宗教的、民族的にどのような意味を持っているのかという視点を持ちあわせつつ調査を行っていきたいと考えている。
グロフィレー,アンヌ.2019.『ワックスプリント:世界を旅したアフリカ布の歴史と特色』ダコスタ吉村花子訳,グラフィック社.
福西隆弘.2014.「第2章 リユース品貿易の実態――古着の国際貿易を事例に」『国際リユースと発展途上国:越境する中古品取引』日本貿易振興機構アジア経済研究所:29-64.
Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.