Cross-border interactions in the China-Myanmar border
Research Background In political geography, a border generally means the separation of national territories into two na…
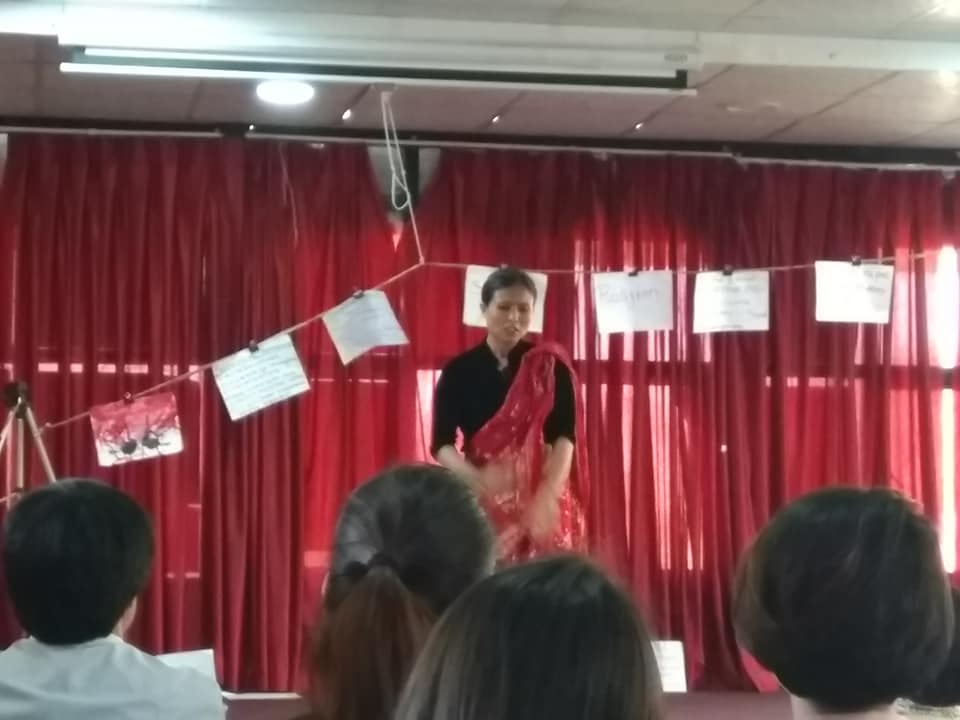
本研究は、現代ネパールの若年女性によるジェンダー規範の実践について明らかにすることを目的としている。とりわけ、路上劇などを用いて女性運動を行う都市部の若年女性たちに注目し、彼女たちの日常における規範の実践と、劇の上演をとおして表出する既存の規範に対する抵抗の両方を分析の対象とした。調査をとおして、家庭内では家族との直接的な衝突を避けようと月経規範や婚姻規範などのジェンダー規範を「正しく」実践したり、遵守するふりをしたりしている若年女性も、演劇という一時的に生み出される虚構の場においては、堂々と規範に対して疑問を呈し、観客たちを巻き込んで議論の場を作り出していることが明らかになった。劇の上演という実践は、調査対象者の女性が親族などとの直接的な衝突や、規範の逸脱によるサンクションを受ける危険を回避しながら、安全にジェンダー規範に働きかける場を提供している。
本研究は現代ネパールの若年層による社会規範の実践について明らかにすることを目的としている。とりわけ、路上劇など応用演劇の手法を用いて女性運動を行う都市部の若年女性たちに注目し、彼女たちの日常におけるジェンダー規範の実践と、劇の上演をとおして表出する既存のジェンダー規範に対する問題意識および規範への抵抗の両方に焦点を当てていく。2019 年にネパールにおいて実施した調査では、路上劇やデモなどをとおして既存のジェンダー規範に抗議する活動を行っている女性たちであっても、家庭内においては既存の規範を実践したり、遵守したふりをしていたりするということが明らかになった。本調査においては、二つの図書館における文献収集をとおして、先述のような調査対象者の日常的な実践と一時的に生み出された虚構の場である演劇がどのように関係しているのかを検討していきたい。

本節では、アジア経済研究所図書館と津田塾大学図書館における文献調査をとおして得られた本研究の新たな視座について記していく。アジア経済研究所図書館ではネパールをはじめとした南アジア関係の文献を、津田塾大学図書館では演劇やジェンダー、フェミニズム関係の文献を収集した。
本調査をとおして、先述のように調査対象者による日常的な実践と路上演劇の両方を
分析対象とする場合、「パフォーマンス」という分析枠組みが有用であるということが明らかになった。ここでいう「パフォーマンス」とは、「見る者、あるいは参加する者が、たとえ無意識であっても何らかの働きかけを受けるような行為や表象」(高橋2005:10)のことを指す。すなわち、パフォーマンス研究とはパフォーマンス・アートの研究と同 義ではなく、その研究対象は日常における様々な実践から大衆芸能や前衛演劇、古典やオペラ、さらに宗教儀礼や国民国家により執り行われる行事やスポーツまで多岐に渡る(高橋 2001:112)。
そうした視座から調査対象者の女性たちの日常生活におけるジェンダー規範の実践と、一時的に生み出される虚構の場である演劇の関係性について検討していくと、彼女たち が行っている路上劇のパフォーマンスは、ターナー(1981)が「リミナリティ(境界性)」という言葉を用いて示したように、価値が一時的に停止して、遊戯性に取って変わられる特別な時間や空間に生起するものであるといえる。高橋(2001)はパフォーマンスが示すリミナリティについて、「パフォーマンスの終了とともに日常の秩序が回復されるが、パフォーマンスは既存の価値観を揺り動かし、対抗的な言説を創造することもある」と述べている。劇の上演という実践は、調査対象者の女性たちが親族などとの直接的な衝突や、規範の逸脱によるサンクションを受ける危険を回避しながら、安全にジェンダー規範に働きかける場を提供することができるのではないだろうか。
本研究では、現代ネパールの若年女性によるジェンダー規範の実践や規範に異を唱える路上劇の事例を扱ってきた。今後はそうした女性たちによるパフォーマンスが、他の南アジア地域の同様の事例と比べてどのような共通点および相違点を持っているのかという点も検討していく必要があるだろう。例えば、インドでは1970年代に路上劇が上演され始めた時には既にフェミニズム演劇の萌芽が見られ(Singh 2009:152)、パキスタンでは1979年に女性の地位向上を目指す「テヘリーケ・ニスワーン」のような劇団が生まれた(Kermani 2021)。今後はこのような他地域における同様の事例を参照しながら、ネパールの若年女性が既存のジェンダー規範に対して抗議するようになるまでの過程や、路上劇などを用いた抗議活動そのものについて研究していきたい。
Kermani, Sheema. 2021.「女性の地位向上のための演劇」村山和之訳『国際演劇年鑑2021―世界の舞台芸術を知る―』pp.49-57.国際演劇協会日本センター.
Singh,Anita.2009.Aesthetics of Indian Feminist Theatre, Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, Volume I, Number 2 , Autumn 2009.
高橋 雄一郎.2001.「パフォーマンス研究をマッピングする」独協大学英語研究(54),pp.109-123.2005『身体化される知―パフォーマンス研究』せりか書房.
ターナー,V. 1981.『象徴と社会』梶原景昭訳、紀伊国屋書店.
Copyright © 附属次世代型アジア・アフリカ教育研究センター All Rights Reserved.